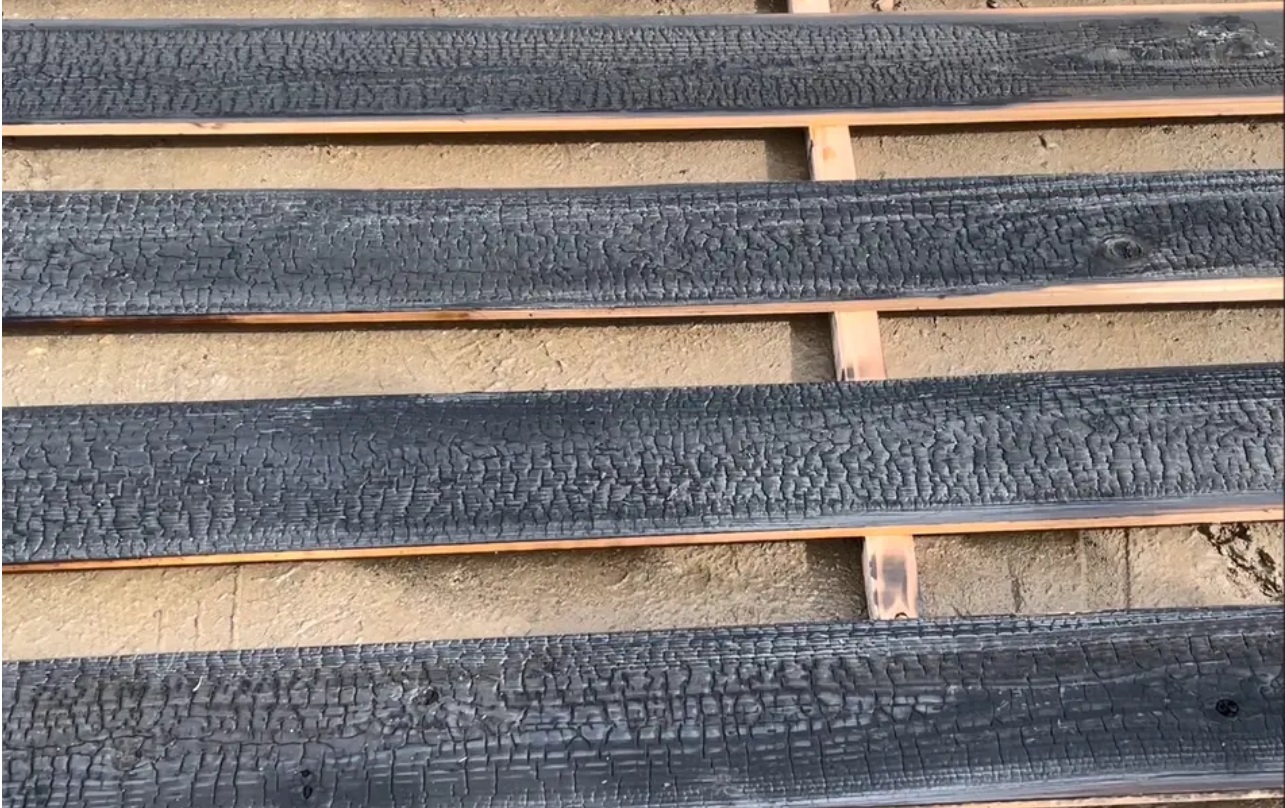家族のストレスを減らす収納ルール 〜書類も学用品も“仕組み化”でスッキリ〜
- 収納
- 家事ラク
- 快適
- 整理整頓

共働き家庭にとって、家族全員が使う書類やプリントの管理は、思った以上に手間とストレスのもとです。学校や保育園からの連絡プリント、医療の書類、公共料金の請求書、各種申込書…。気づけば山のように積み上がり、「どこに何があるか分からない!」と慌てることもしばしば。そんな状態は、忙しい日常の中で家族の情報共有を難しくし、見落としや期限切れのトラブルも招きかねません。
そこで大切なのが、「家族で共有できる書類管理ルール」をつくること。
夏休みも終盤ですね。新学期からゆとりのために、宿題を頑張る子供たちの横で、大人は書類管理の仕組みを完成させていまいましょう。
1度つくれば、ずっと使える仕組みになります。
1.まずは「定位置」を決める
書類が散らばる原因の多くは、置き場所が決まっていないこと。
ダイニングや、リビングの目につく場所に、「書類専用とりあえずボックス」を設置しましょう。ファイルボックスやトレイを使い、家族全員がアクセスしやすい場所におくことがポイントです。ここに、届いた郵便物、学校から持ち帰ったプリントは必ず一旦置くルールを作ります。
2.「捨てるタイミング」をルール化
溜まった書類の管理でよくある悩みは「いつ捨てていいのかわからない」こと。
不要な書類を放置してしまうと、また散らかりの元になります。
一旦置いておいたボックス内の書類は、月に1回見直しの日を決めます。
私の家庭では、支払いの確認も兼ねてお給料日に設定していました。
「書類整理」と、カレンダーアプリに入力しておき、その日が来たら整理します。

3.期限や重要度で「見える化」する
書類は「ただしまう」だけでなく、期限や重要なものは家族全員がすぐ分かる工夫が必要です。カレンダーやホワイトボードを設置し、支払い期限や提出期限を記入しておくと、忘れ防止になります。また、重要な書類には付箋やマグネットで目印をつけておくと家族の目にも入りやすくなります。
4.保管管理が必要な書類は、カテゴリーに分けて保管
大量の書類も、「種類別」に分けることで探しやすくなります。
ルールを決めた書類管理の収納スペースを、わたしは、情報ステーションと名付けています。「ここを確認すれば、家族みんなが必要な書類を一目でみつけることができる」
そんなタイトルをつけていきます。
学校・保育園関連
医療・保険関係
公共料金・支払い関連
申請・手続き関連
など、家族の生活に合わせたカテゴリーを設定し、ファイルボックスや、フォルダーに名前を書いて整理します。
家族の共有書類・プリント管理は、「定位置」「定期整理」「処分ルール」「分類」「見える化」の5つのポイントを押さえれば、ぐっとストレスが減り、忙しい毎日も安心して過ごせます。
書類の管理は、収納をつくるだけでなく、「運用のルール」がポイント。
少しの工夫で情報の混乱から解放され、家族みんなが気持ちよく生活できます。
後回しにしがちな書類管理ですが、効果は高いのでぜひ取り入れてみてください。
「家族のストレスを減らす収納ルール」
書類も学用品も、仕組みがあるかどうかが大切です
私が整理収納サポートを担当した、Aさんご一家のリアルストーリーをご紹介します。今回は、学用品と、おもちゃの仕組みづくりです。
学用品の置き場所のbefore→after
どうしたら定位置に置いてくれるんだろ…悩みますよね。
その問題が起こっていた時の学用品の置き場所は、リビング横に隣接した和室で、帰宅動線からは少し離れています。徒歩で帰ってくる小学生は、汗をかき疲れて帰ってきます。一刻も早くランドセルを下ろしたい!そんな気持ち、わかる気がします。なので、リビングドアを開け、1歩でたどり着く場所にオープンラックを設置。ランドセルの定位置は、背中からおろし、そのまま置ける3段棚の1番上につくりました。

収納用品の選び方も大事
新1年生になるとき、学習机を購入されるご家庭が多いと思いますが、それとセットで、ランドセル、教科書、文房具、ファイルなどの収納がシステム化された収納、見られたことないですか?それを使われていたのですが・・・正直、私は、使いこなしているお子さんをみたことがないんです。
収納って100人いたら100通りの使い方があるので、多様性のあるシンプルな収納を選ぶことをオススメします。また、子育てで使う収納は、実家を出ての大学生活にも使えるものを選ぶといいなとも経験から思います。

教科書やノートを教科ごとに分類した収納の意味は?
ランドセル置き場が決まり、次は教科書や、プリント、返ってきたテストの定位置です。
Beforeの収納時に、「教科書とノートを教科ごとに分類して収納している意味は?」と聞くと、「わかりやすいかと・・・」
うんうん、わかりやすいです、確かに。確かにそうなのですが、片付け=元あった場所に戻すことができなくて悩んでいるのだとしたら、ルールを緩くしてあげることが有効かもしれません。小学生の間は種類も少ないので、大まかに、「教科書とノート」「プリント」と単純な分類で定位置を決めていくのもあり!
学習に遊びに頑張った1日の終わりですもの。ルールを単純化して、ストレスなく片付けてしまいましょう。
増え続けるおもちゃ。どうして???
次におもちゃに取り掛かります。
「とにかくすごい量でびっくりされると思います・・・」と子供部屋へ案内いただいたところ、確かに小学生のお子さんには管理が難しい量でした。
どうしてこんなに増えたのか、もう少し掘り下げてヒアリングが必要だったのですが、今回の作業時間内にはたどり着けないだろうと判断し、整理の進め方を伝授、進まなければ、次回もう一度ご依頼いただくことにしました。
つまり、おもちゃ収納=子供部屋は、今回解決できなかった場所です。
悔しいですが、お子さんと一緒のほうが解決しやすい場所でもあるのでこれで良し!なのです。

整理収納にとりかかったその未来
Aさんファミリーの悩みはこうでした。
『お子さんがおもちゃを片づけてくれない』『ランドセルも中身も床に置きっぱなし』この悩みは解決したか。
少しは解決したんじゃないかなと思います。ただ、今回、私たちがサポートしたのは、収納を仕組化し、景色(環境)を整えただけ。スムーズな収納の仕組みが準備できたらここからが本番です。
「みんな一緒に楽しい週末を過ごしたいから、だから頑張ろうね」と、目的を家族で共有し、楽しみを計画すること。
子供たちが「片付け=もとあった場所に戻す」ことが習慣として身につくまでは、忍耐強く声をかけ、信じて、見守り、出来たら褒めること。
その先の未来には、スッキリした部屋の快適さが理解でき、自分にとって必要なものを選択する力、自分のことは自分でできる自立した生活力が手に入っているはずです。
一長一短にはいきませんが、向き合わなければ、手に入れることができなかった未来かもしれません。Aさんファミリーは、その1歩を踏み出しました。そろそろ報告がくるころかなと思います。その時は、また書きますね。
次回は、受験勉強編。
世界一幸せな暮らしを収納で叶える。子供部屋とキッチンの話し。
お楽しみに^^

Kuraduce(クラデュース)代表
浮田美紀子
(一社)ハウスキーピング協会認定。整理収納アドバイザーとしての経験を活かし、「ゆとりある暮らし」をサポートするKuraduceを設立。住まいや家事の支援、生前整理、家族のための準備など、暮らしを多面的に支えるサービスを展開中。心に寄り添うサポートを大切にしている。