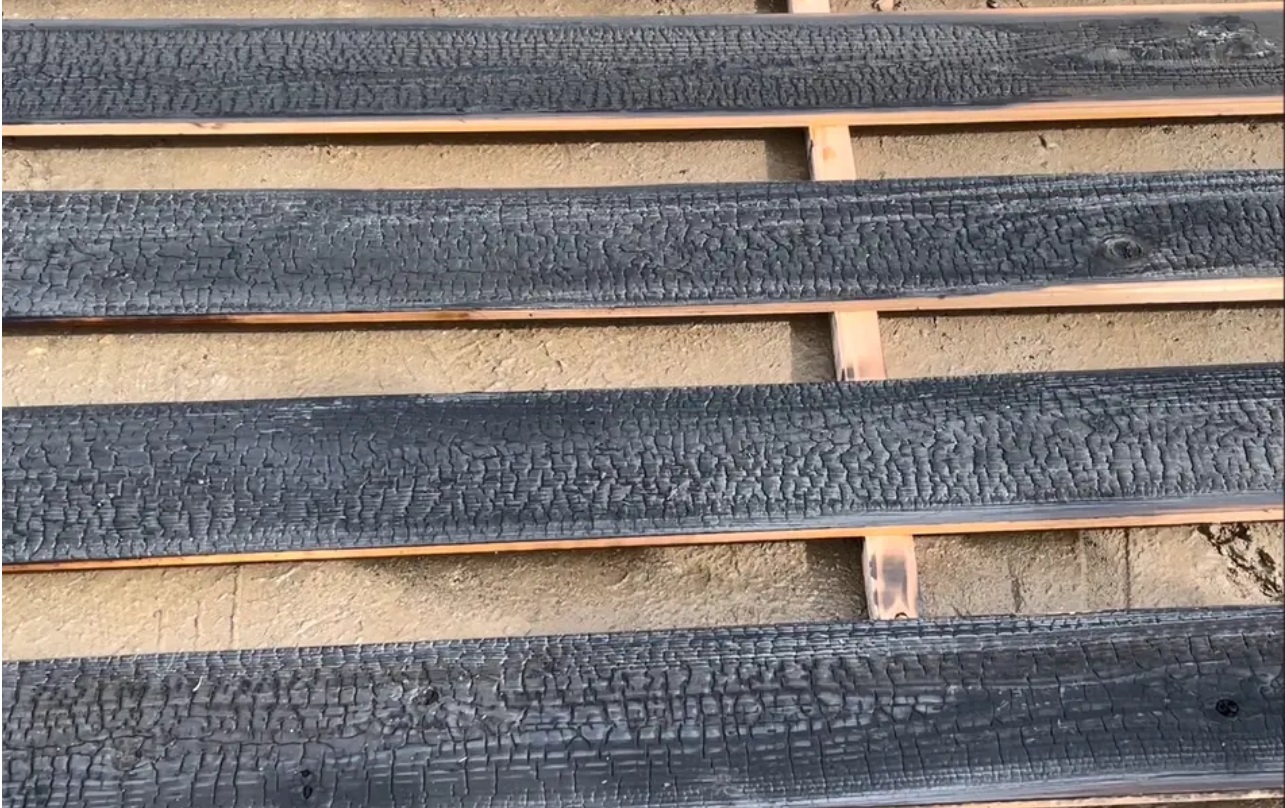“働くって、素敵なことかも。”──ともに育ち、ともに未来をつくるための、わたしたちの小さな挑戦

就職活動がそろそろ現実味を帯びてくる時期──大学3年の学生たちの表情には、「そろそろ動き出さなきゃ」という若干の焦りと、“どこか遠いもの”だった「働く」が、少しずつ自分のこととして感じられ始めているような空気があった。
「生活のため」「とりあえず就職」「趣味の時間が確保できるなら」──
そんな声は、今の学生にとって決して珍しくない。
だがそれは、「怠けたい」わけではない。まだ、“働くことの意味”や、“社会人としてどう生きていくのか”に触れたことがないだけかもしれない。
私たち米田木材は、そんな今だからこそ、「働くってどういうこと?何のため?」という問いを学生に投げかけてみたかった。幸せな暮らしをつくる仕事をしている私たちだからこそ、“働くこと”が持つ意味や、仕事を通して人に価値を届けることの手応えを、若い世代に伝えられるのではないか──そう考えたのだ。
そんな問いを、どうすれば学生たちに“届く形”にできるか──私たちは、「講義」というかたちに託してみることにした。
そうして実現したのが、富山国際大学・観光専攻での出前授業。
講義タイトルは『“届ける”というしごと 〜観光も、建築も、そして人生も〜』。
講師を務めたのは、米田木材の採用担当であり、入社6カ月目の堀 百利だった。23歳という若さで学生の前に立ち、自らの言葉で“働くこと”のリアルを伝えた。学生と年齢が近いからこそ、伝えられることがある。社会に出たばかりだからこそ、見えることもある。
そしてその背後には、堀を送り出した米田亮樹の想いがあった。
この出前授業は、単なる企業紹介や採用活動ではない。「“働く”ということに、向き合う時間にしたい」──そんな想いから始まった、ちょっと熱い授業だった。
講義に込められた想いと舞台裏、そして語り手たちが見つめた“働くということ”をめぐる記録である。
「“働く”って、自分で決めていい。」
今回、米田木材が訪れたのは、富山国際大学の観光専攻の講義。たとえ学んでいる分野や目指す業界が違っても、「働く」ということの根っこは、きっと誰にとっても共通しているのではないか──そんな思いが、この講義の出発点になった。
今回の講義のタイトルは、『“届ける”というしごと 〜観光も、建築も、そして人生も〜』
学生たちに届けたかったのは、「職業」や「業界」を超えて、自分自身の価値観から“働く意味”を見つけていこうというメッセージだった。

講義を受けたのは、就職活動がこれから本格化していく、現代社会学部・観光専攻の3年生たち。これからの未来を選択する彼ら・彼女たちは、どこかで「学んできたことを活かさなければ」「専攻に合った企業に就職しなければ」といった“なければ”という枠にとらわれてしまう瞬間がある。
けれど、本当に“働くこと・職業を選択すること”は、学んだことや専攻だけで決めなければならないものだろうか?
大切なのは、「どこで働くか」「何をするか」だけではなく、“誰のために、どんな価値を届けたいか”──そんな問いから始まる選択があってもいい。
そして、業種や職種の違いを越えて、「自分の価値を誰かに届けたい」と願う人たちに、“働く”とは、もっと自由で、おもしろくて、誇れることなんだ──そんな想いを届けたい。それが米田木材が、この講義に込めた願いだった。
入社半年の彼女が“語り手”になった理由
今回の講義で語り部を務めた堀は、まだ社会人としてのキャリアは長くない。実績でいえば、上司や先輩社員のほうが豊富かもしれない。それでも、講師として学生の前に立ったのは、なぜだったのか?
そこには、リクルーティング・コミュニケーション室の立ち上げを担ってきた亮樹の、明確な狙いがあった。
「企業としてどんな価値を届けているかを話すなら、社長や役員が語るべきかもしれない。でも“働くってどういうことか?”を、これから社会に出ようとしている学生に伝えるなら、“今まさにそのプロセスにいる人”の言葉の方が届くと思ったんです」

堀は、つい最近まで“就活生”だった。将来に迷い、進路に悩み、「働くって、なんなんだろう」と問い続けた時期がある。だからこそ、学生たちと“目線の高さ”が近い。社会人として大人びた言葉ではなく、ひとりの若者として、実体験に基づいたメッセージを語れる存在だ。
そしてもうひとつ、大きな理由がある。
堀は、入社してまだ間もない頃から、会社が大切にしている考え方や想い、世界観を自分の言葉で語る努力を重ねてきた。その姿勢に、亮樹は可能性を感じていたという。
「最初からうまく話せたわけじゃない。けれど、話すたびに“これは社長の言葉ではなく、私の想いです”と言えるようになっていった。そんな彼女だからこそ、学生に伝わるものがあると思ったんです」と亮樹が語る。
“大切にしている考え方や想いを語れること”は、知識や暗記ではない。心の底から「そうありたい」と願い、自分の中に根づいたものだけが、言葉になる。そしてそれが、本気で誰かに伝え、届いたときに、相手の心を動かす。
堀はその「伝える」という挑戦の、まさに真っただ中にいる存在だった。
だからこそ、あえて堀が語り部として立つことに意味があった。決して、完成された話し手としてではなく、“今、社会人として歩き始めたばかりの一人の人間”として。
講義の場には、等身大の葛藤や、まっすぐな想いが流れていた。
学生の表情が変わっていくのを、見逃さなかった
「生活のため」「趣味を楽しむため」「やりたいことが見つかるまでの一時しのぎ」──仕事そのものに価値を見出せている学生は、まだ少ないのではないだろうか。
だからこそ今回の講義では、「働く=価値(人の役に立ち、喜んでもらう)を届ける営みである」という視点からアプローチした。観光や、建築だけでなく、すべての仕事は“誰かに価値を届ける”という点でつながっている。堀の語る実体験や、米田木材の取り組みを通じて、学生たちに“働くことの本質”を届けようとした。
講義が始まった当初、学生たちの表情はやや硬く、どこか遠巻きに話を聞いている印象だった。けれど、堀が「自分が“何を誰に届けたいか”を考えることで、働く意味が見えてきた」と話し始めると、少しずつ空気が変わり始めた。
「届ける」という言葉が、“就職活動”という枠を超えて、学生一人ひとりの生活や価値観と結びついていく。
「誰に」「どんな風に」喜んでもらいたいのか。それは、観光に限らず、あらゆる仕事にも通じる問いだった。

ワークの時間には、最初は戸惑っていた学生たちが、徐々に自分の内側を言葉にし始めた。「子どもに笑顔を届けたい」「地元の魅力を発信したい」「誰かの安心できる場所をつくりたい」──いくつもの“届けたい想い”が、ワークシートの上に綴られていった。
その変化を、後ろからそっと見守っていた亮樹が、ぽつりとこぼした。
「いい表情、してるなぁ」
学生たちは、“正解のある問い”には慣れていても、“自分の想いに向き合う問い”には、まだ不慣れだ。けれど、それでも向き合い、書いてみようとする姿勢。そのまなざしの変化に、亮樹も堀も、確かな手応えを感じていた。

「たとえ今すぐ答えが出なくてもいい。“届けたいもの”を考えるという体験そのものが、いつか“働く意味”につながっていくと思うんです」──亮樹のそんな言葉が、印象的だった。
講義の後、学生たちのアンケートには「働くことの見え方が変わった」「“価値を届ける”という視点は初めて考えた」といった声が並んだ。
知識や就職情報だけでは届かない、“心が動く瞬間”。
学生たちの心の中に“働くこと”への肯定的な感情が芽生えているように感じた。

私たちにとっての 「働くとは」
講義の終盤、堀は学生たちに向けて、こんな問いを投げかけた。
「あなたにとって、“働く”ってなんですか?」
これは、堀自身が新卒で社会に出るとき、自分に問い続けてきた言葉でもある。「やりたいことが分からない」「向いている仕事って何?」──そんな焦りや不安の中で、何度も心の中で問い直してきた。
堀は、前職では大手企業の一員として働いていた。けれど、日々の仕事が、誰のために、何のためにあるのか──その実感がつかめず、葛藤を抱えていた。そんな時に出会ったのが、米田木材だった。
「地域に生きる人の暮らしを、家づくりで支える」「社員一人ひとりの想いを大切にし、“自分らしい働き方”を応援する」
そうした理念に共感し、入社を決めた。けれど、共感しただけで“自分のもの”になるほど、会社の想いや考え方は簡単なものではなかった。入社後、堀は何度も言葉と向き合い、自分の言葉で語れるように、ノートに何度も書き写した。朝礼や研修で何度も語られる「理念」は、決して上から押しつけられるものではなく、“自分に引き寄せて考える”ことを求められるものだった。
そうやって少しずつ、「自分にとって“働く”とは何か」が言葉になっていった。

学生の前に立ち、語りかける堀の姿を見ながら、亮樹は改めて“働く”ということの本質に思いを巡らせていた。
亮樹が考える「働く」の意味は、明確で力強い。
「働くとは、今この時代に求められていることに、自分の力で応え、社会や人の役に立つ価値を届けること。」
誰かの役に立ちたい、喜んでもらいたい──そんな想いを、自分自身の手でかたちにしていく営みこそが、“働く”ということの本質なのだと語る。
そしてその考えの背景には、「先代に感謝し、次代に貢献」がある。
「自分たちが今ここで働けているのは、これまでこの会社を支えてきてくれた人たちがいたから。だからこそ、次の世代が希望を持って働けるように、今の私たちが何を残すのかが大事なんです。」
目の前の数字だけを追いかけるのではなく、社会の一員として、自分の力でどんな価値を世の中に届けられるか。
「“働く”とは、“役に立つ”ということの本質的な表現だと思うんです。その時代に必要とされていることに応えようとする姿勢こそが、仕事であり、生き方なんじゃないかなと。」
亮樹にとっての「働く」は、目の前の業務だけにとどまらない。
それは、世の中と対話することでもあり、未来に向けた責任の引き受けでもある。
学生たちにとって、“働くこと”はまだ先の話かもしれない。
だけど、この日交わされた言葉たちは、きっとどこかのタイミングで思い出されるはずだ。
学生たちがこの講義を通して気づいたこと、学んだこと、そして小さくても実際に動き出した一歩──そして、それらが次の世代に受け継がれていき、「働くことって、素敵かも」という前向きな気持ちと、そこから生まれる行動が連鎖し、やがて社会全体を少しずつあたたかく変えていくのではないだろうか。
堀が問いかけた「あなたにとって“働く”とは?」という一言。
それは、学生たちにだけでなく、私たちにも返ってくる問いだった。
社会に出る直前の学生。
歩き出したばかりの社会人。
組織を率いる経営者。
立場は違っても、「働くとは何か?」という問いに、“これで完璧な答え”などない。
でも、自分の言葉で、自分なりの意味を探そうとすること。
誰かのために何かを届けようとすること。
その一歩が、“働く”という行為を少しずつ自分のものにしていく。
講義が終わった後も、学生のまなざしには、どこか余韻のようなものが残っていた。
きっといつか、就職活動の途中で、あるいは社会人になったときに、思い出すはずだ。
──あの時、自分に問われたこと。
「じゃあ、あなたにとって、“働く”って何ですか?」
その問いの答えは、これからの人生で、何度でも書き換えて大きくしていけばいい。
私たち米田木材は、これからも「“働くとは?”の問いと、共に生きる人」を応援し続けたいと思っている。
採用担当 リクルーティング・コミュニケーション室

堀 百利(ほり ももか)
米田木材初の採用担当専任者として2024年12月に入社。富山大学芸術文化学部出身。自身の就職活動を通して企業と学生との出会いに魅力を感じ、採用担当者を志すようになる。好奇心・探求心旺盛で、様々な分野に興味があるが、特に好きなものは日本酒。人生理念は“人との出会いを大切に”。
タグ

YG TIMES編集員
柏木 彩夏
2019年に中途採用で入社し、現在は入社7年目。所属は事務部だが、部署を超えて色々な業務にチャレンジしている。YG TIMESの編集やインナーブランディングに携わる。昨年育休を終えて職場復帰。職場での学びを育児にも活用し、豊かな暮らしを実践中!